サプライチェーンマネジメントの現場から~災害・地政学リスクに強いSCMとは

Report|2025年2月20日
この記事は約5分で読めます
サプライチェーンマネジメント(SCM)の難しさが増しています。激甚化する災害や戦争などの地政学リスクが、グローバルな調達・生産・物流・販売網に与える影響は想定を超えるようになっています。企業がいかなる時にもビジネスを継続するためには、いま、サプライチェーン改革は不可欠です。
2024年、SCMが直面する課題を考えようと、国内外に供給網を有する企業と共に共通の課題について議論することを目的にラウンドテーブルが企画されました。この度、4回に渡る会合から課題解決に向けた提案などをまとめ、『ダイナミックサプライチェーンを構想するラウンドテーブルReport』を刊行いたします。
刊行にあわせ、サプライチェーンの最前線でどのような変化が起きているのか。また、異なる業種企業との意見交換を通じて考えたSCMのあるべき姿などについて、参加者に振り返っていただきました。
(画像左から:富士通株式会社 瀧澤 健、サントリーホールディングス株式会社 竹本 宏志 氏、セイノーラストワンマイル株式会社 河合 秀治 氏、東京海上レジリエンス株式会社 堀内 伸 氏 、東京海上日動火災保険株式会社 小林 且弥 氏)
※所属・役職は取材当時(2024年11月)のものです。
本ラウンドテーブルには、以下の4社に参集いただきました。原料調達網が世界に広がるサントリーホールディングス、ドライバー不足など2024年問題に挑む物流業界からセイノーラストワンマイル株式会社、多様なリスクに企業を知識と経済面で支援する東京海上レジリエンス株式会社と東京海上日動火災保険株式会社です。4社と富士通のサプライチェーンの担当者が膝を突き合わせ、SCMの課題や強じん化について、熱く語り合いました。
[原料調達の現場から] 異常気象と地政学の複合リスク!原料が手に入らない?
「異常気象に加えて地政学のリスク――『こういうことはあるよね』と思っていた常識が崩れていくような感じです」サントリーホールディングス株式会社の竹本 宏志 氏の感じた危機感は、原料調達の現場にありました。
年間約6億ケースもの商品が流通する サントリーホールディングスのサプライチェーン。この内、常に需要があるオレンジジュースの産地に、異常事態が起きているのだといいます。まず、世界最大のオレンジ産地・ブラジルで、高温などで病害が発生。収穫量は前年度比の約4分の3以下です。さらに、アメリカの産地・フロリダ州がハリケーンに立て続けに襲われ、大被害が出ました。「世界のどのホテルでも、朝の食卓にオレンジジュースがないというわけにはいきません」と竹本氏は、企業としてオレンジジュースは欠かせないと説明します。「世界各地の産地に担当者が飛んで、必死に代替産地を探しました」

執行役員 サプライチェーン本部 副本部長 竹本 宏志 氏
なんとかイスラエルのオレンジ農場を確保し、ほっとしたのは束の間でした。イスラエルとガザの間で戦闘が勃発し、その余波で中東の武装グループが、商船をミサイルで攻撃するようになったのです。世界の大動脈・スエズ運河が通れない緊急事態です。「産地が壊滅するような異常気象。それに加え、突発的な地政学リスク――15年以上調達に携わってきましたが、こんなことは初めてでしたね」と竹本氏。世界的にオレンジ果汁の値段が高騰する中、竹本氏は果汁の組み合わせを工夫した「代わりのレシピ」を考え出すことで、なんとか出荷ゼロの危機を回避できたということです。
ラウンドテーブルで、サプライチェーンの想定を超える「不確実性」を共有した竹本氏。サントリーホールディングスは、業務系の基幹システム刷新をはじめ、SCMの強じん化に数百億円をかけて取り組み始めているということです。
竹本氏に、ラウンドテーブルを振り返った感想を聞きました。
「作物の産地がおかしくなっているという体感が、何年後にどうなるか、計算したくてもしようがないと思っていました。ラウンドテーブルに参加して、統計的に処理された良質なデータが増えていることを知ることができました。これからデジタル化が進めば、こうした客観的なデータを元に、説得力のある短期計画や中長期的な戦略を立てられるようになるのではと期待しています」 (竹本)
[物流の現場から] 物流が寸断された被災地でセイノーのドローンだけが飛べた理由とは
ラウンドテーブルの議論において、サプライチェーンを止めないためには、何もない「平時」のフェーズから「有事」の準備をする「フェーズフリー」という考え方が大切だと強調したのは、セイノーラストワンマイル株式会社の河合 秀治 氏です。
河合氏は新規事業領域を担当しており、環境整備が急ピッチで進むドローンによる配送に力を入れています。
ドローン配送の「フェーズフリー」の取組みが注目されたのが、2024年元旦に発生した能登半島地震です。
最大震度7の揺れで土砂崩れなどが多数発生。国道が寸断され、多くの集落が孤立しました。全国から物資が集まりましたが、道が通れず立往生するトラックが相次ぐ中、セイノーラストワンマイルとプロジェクトを組むエアロネクストのドローンだけが、支援物資を積んで飛び、孤立地域に届けることができました。
「現地で体制が取れていないと、1日や2日では何もできません。日ごろから対策をインストールしておいたことが、大きなポイントだと思います」と河合氏。

セイノーホールディングス株式会社 執行役員兼任 河合 秀治 氏
セイノーホールディングスでは、以前から社会課題として、過疎地域への配送に取り組んでいました。ドローンのテストを重ねる中で浮上した課題の一つが、寒すぎるとドローンが動かなくなることでした。
「北海道や山梨の過疎地域でテストを始めましたが、そうした中山間地でドローン配送が必要なエリアは冷えるんですね。冬はしょっちゅうマイナスになります。だから、ドローンは寒さに対応できるものでないといけないと考えました」
寒冷地でも飛行できるドローン開発のため、気温がマイナス25度のモンゴルに行きテストを繰り返しました。準備の積み重ねがあってこそ、氷点下の被災地ですぐに活動に移ることができたと、河合氏は振り返ります。
サプライチェーンの途絶に、新しい物流手段のドローンの可能性が実証された今回の地震。現在、国は地域の防災計画に、ドローンを積極的に取り入れるよう指導するなど、基盤整備を推進しています。
河合氏は、「フェーズフリー」の取組みでは、平時から地域のサプライチェーンやリスクをデジタル化して『見える化』し、有事に他社と共有できるようにすることが大切と考えています。
「例えば、災害で孤立しそうな地区について、普段からドローンの航路を設定しておいてシステムでデータを共有しておく。そうすれば災害が起きた際に、他の業者や自治体のドローンでも飛べるようになります」と河合氏。
また、物流業界では「2024年問題」と呼ばれるドライバー不足が深刻な課題です。データを共有する共同配送の仕組みなどデジタル化が求められていますが、経営基盤が弱い中小企業が多い、競合との競争が激しいなどの理由で、推進は簡単ではありません。
そうした中、河合氏は有事に協力しあう協調領域について話し合うことで、社会の強じん化を考えていけるのではないかと指摘します。
「デジタルなサプライチェーンは、物流の真の効率化につながるのではないかと思うんですね。 今回のラウンドテーブルを経て、全く異なる業種の企業さんと議論ができたことで、物流だけで考えるのではなく、俯瞰して社会全体について考えることができました」 (河合)
[保険業界の現場から] リスクマネジメントに必要な「3つの可視化」とは
「自然災害のリスクは、頻度(フリークエンシー)と甚大度(ダメージャビリティー)の、両方が急激に増加しております。保険会社としての保険金の支払い件数と支払金額についても同様に急激な増加傾向にあります。このため、自然災害リスクについての保険引受が非常に難しい局面になってきております。」と話すのは、東京海上レジリエンス株式会社の堀内 伸 氏です。
サプライチェーンが災害などで寸断された際、企業が頼りとするのが保険です。しかし、自然災害が甚大化する中で、平時でのサプライチェーンを俯瞰したリスクマネジメントの高度化が強く求められる時代になってきていると堀内氏は話します。
再保険大手のスイス再保険のまとめによりますと(*)、2023年に同社が保険金を支払った災害の数は過去最も多くなりました(142件)。また、災害の保険損害の負担は、過去30年間で2倍以上になったと推計されています。
「単純に自然災害が増えているだけではなく、対応するリスクの種類も増えています」と堀内氏。

持続可能な企業経営をするためには、サプライチェーンの潜在的なリスクも可視化して、その対応策を準備しておくことがリスクマネジメントとして求められております。弊社は、多くのお客様の生産拠点に訪問させていただき、現場等を拝見させていただいた上で、事故削減に関するアドバイスをさせていただいております。
また、サプライチェーンに関するリスクマネジメントの高度化に必要となると考えているのが「3つの可視化」です。
第1に、「サプライチェーンの構造の可視化」です。サプライチェーンの構成企業を可視化して、構造のどこで、どのようなリスクがボトルネックになっているのか把握すること。
第2に、サプライチェーンの階層であるティア1、2、3のそれぞれの「拠点ごとのリスク」を洗い出すこと。そして第3に、各階層を通る「物流」を可視化しておくことです。
「サプライチェーンのリスクマネジメントの高度化については、現在、保険会社がご提供させていただいているソリューションから、さらに広範かつ高度化していかなくては対応が困難な時代になってきている。弊社も、その高度化支援に資するソリュ―ションの開発/提供も進めております。」と堀内氏は指摘します。

営業企画/アライアンス部 部長 堀内 伸 氏
「ラウンドテーブルに参加して、SCMといっても、食品・物流・保険・ITと4社あれば4様の関心事があることがよくわかりました。我々は富士通さんと比較的近い立場で参加しましたが、業界ごとに課題があって、集約するのは難しい議論でしたね」と堀内氏はラウンドテーブルを率直に振り返ります。
「それでもリスクに備えて、可視化するにしても平時の対策を策定するにしても、データがないとできないと実感しました。またそのデータ量も膨大になるので、デジタル技術の活用は不可避と改めて感じました。ただ、各社・業界ごとに成熟度は違うので、それぞれに合わせて対策する必要があると見えたことが、大きな収穫でしたね」 (堀内)
サプライチェーンのデジタル化は社会課題解決への道
「サプライチェーンをデジタル化することで、社会のダイナミックな変化に追従できるようになると思っています」と、ラウンドテーブルを主催した富士通の瀧澤 健は強調しました。
瀧澤が言う「ダイナミック(動的)な変化」とは具体的にどのようなことかーーラウンドテーブルでは、リスクの多様化について繰り返し問題が提起されました。ラウンドテーブルにおける議論では、東京海上日動火災保険様が整理されたリスク一覧として地政学や公衆衛生、人権など、15項目が並びました(図1)。それぞれの項目のどこにリスクが潜在するのか、可視化を進めることが重要だという点で参加者の意見が一致しました。

さらに瀧澤は、SCMのデジタル化は、環境などの社会課題にアプローチする上でも価値があると指摘します。
「平時からデータをデジタル化して利用していると、判断の選択肢が増えるんです。例えば、飲食や小売りで無駄が出ない食材の数を発注したいと考えたとします。これは気温の変化や来客数など、常に変化するデータをもとに予測した方が、最適解に近づけます。そしてフードロスが削減できます。サプライチェーンのデジタル化は、本来の企業の価値を向上させるだけではなく、社会課題に寄与する一丁目一番地でもあると思っています」

グローバルソリューションBG エグゼディレクター 瀧澤 健
社会課題の解決には1社だけで挑んでも限界があります。瀧澤は、枠組みを超えて協力していくためには、競合他社のデータを互いに見えないようにするといった業界の実情に合わせた工夫も重要だと改めて実感したといいます。
「競合他社に自社のデータは使われたくないですよね。富士通が提供するデータ基盤には、『この領域ではデータを共有していい、この領域は使ってはいけない』という線引きができる機能があります。こうしたツールをもっとうまく使っていけたらと思います」
「富士通としては、お客様の分断されたデータをアグリゲーション=統合して便利な形でお客様に提供していきたいです。SCMにあるリスクを可視化し、有事に共同で活用できる仕組みづくりをリードすることで、ゆくゆくは業界、社会全体がいかなる有事にも活動を継続できるようご支援をして参ります」 (瀧澤)

この度刊行する『ダイナミックサプライチェーンを構想するラウンドテーブルReport』は、広範なサプライチェーンを有する企業が直面する課題や、変革への提言など、幅広い議題を取り上げました。ぜひダウンロードして、事業変革の一助としていただければ幸いです。
竹本 宏志
Hiroshi Takemoto
サントリーホールディングス株式会社 執行役員
サフライチェーン本部 副本部長
1990年サントリー株式会社に入社。洋酒や飲料の原料調達から始まり、スピリッツ生産部長、ビームサントリーアジアCSCOを歴任。2023年よりサプライチェーン本部副本部長、戦略本部長を務める。SCM DXプロジェクトに参画・推進。2024年サントリーホールディングス株式会社執行役員就任。

河合 秀治
Shuji Kawai
セイノーラストワンマイル株式会社
代表取締役社長
セイノーホールディングス株式会社
執行役員兼任
トラックドライバーとしてキャリアをスタートし、社内ベンチャー、ココネット株式会社を2011年に設立。
同社が取り組む社会課題解決型ラストワンマイル事業の展開を図るため、2024年4月事業持株会社セイノーラストワンマイル株式会社代表取締役社長に就任。傘下6社の代表取締役、セイノーHD執行役員 ラストワンマイル推進チーム担当、オープンイノベーション推進室長を兼務し、CVC「Value Chain Innovation Fund」などを管掌。

堀内 伸
Shin Horiuchi
東京海上レジリエンス株式会社
営業企画 / アライアンス部 部長
1991年に東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社。総合商社、化学産業、自動車産業のお客様にリスクマネジメントを支援する営業部門を経て、自動車産業をグローバルの支援する企画部門、シンガポールにて弊社のアジア拠点の経営管理、営業戦略を立案する中間持ち株会社を経て、物流/サプライチェーンリスクのマネジメント高度化を支援するソリューション/保険商品の開発の部門を経て、2024年より現職。

小林 且弥
Katsuya Kobayashi
東京海上日動火災保険株式会社
マーケット戦略部 企画戦略室 マネージャー
1992年に東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社。総合商社、エネルギー産業、自動車産業、食品・製紙・医療・半導体産業のお客様に損害保険とリスクマネジメントを支援する営業部門の他、ベルギーにて欧州・ロシア・アフリカ地域の特定自動車メーカーの損害保険とリスクマネジメント支援、シンガポール損害保険事業会社の経営、等に従事。2024年より現職。

瀧澤 健
Ken Takizawa
富士通株式会社
グローバルソリューションBG
クロスインダストリーソリューション事業本部
工グゼディレクター
富士通グループのプロダクト系ビジネスにおけるプロセス改革責任者として、S&OPから、製品設計~製造~調達~物流など、全社オペレーション改革を推進。また、工場再編や海外展開、スマートファクトリなど、グループ横断のものづくり改革を牽引。
2020年からは、富士通初のDXコンサルティング会社の立ち上げに経営メンバとして参画、経営から現場にいたる製造業向けDXビジネスを牽引。現職では、幅広い産業向けの社会課題解決を目指したUvanceクロスインダストリー事業を担務。
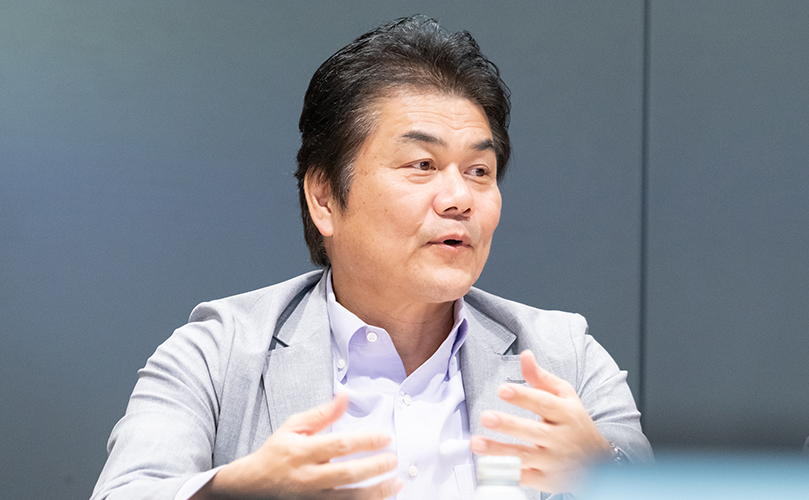
ダイナミックサプライチェーンを構想するラウンドテーブルReport
ラウンドテーブル参加企業から共有されたサプライチェーンマネジメントの事例を基に、これからの社会を支える持続可能かつ強靭なサプライチェーンの構築と運用の在り方、社会全体でのリスク可視化と対応に向けた仕組みづくりについて示唆をまとめています。


関連コンテンツ
BANI時代のSX経営を拓くデータドリブンサプライチェーン変革

