ビジネスアジリティを高める「三位一体」の変革とは

Report|2025年1月27日
この記事は約7分で読めます
非連続で不確実性が高い現代において、ビジネスの予見可能性を保つには相当な困難が伴います。外部環境の変化をリスクや制約ではなく、競争力を高める成長の機会と捉えるカギとなるのは、変化に応じて自らを変革し続けるアジャイルな経営を築くことです。
アジャイルな経営を構築するには①経営層、事業部門、IT部門の間のサイロを打破する「組織」変革②予め計画を立てる事前計画型だけでなく、仮説を立てて検証を繰り返すことで予見可能性を高める仮説検証型を推進する「ビジネス」変革③組織とビジネスの変革の好循環をつくるエンジンとなる「IT」変革、の一体的な取り組みが重要となります。
「組織」「ビジネス」「IT」の三位一体の変革を支えるのはデジタルです。デジタルを柱とした3つの変革の好循環を促し、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じた全社変革に不断に取り組んだ先に、持続的な企業価値向上への扉が開かれるのです。
本レポートの一部を抜粋してご紹介します。全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。
日本のデジタル競争力の現在地
スイスのビジネススクールIMDが2024年11月に公表した「IMD世界デジタル競争力ランキング」の2024年版によると、日本の総合順位は31位と2023年より1つ上げました(図表1)。2017年の調査開始から続いた下落傾向には歯止めがかかりましたが、いまだ停滞しています。1位はシンガポール、2位はスイス、3位はデンマークです。上位10位以内には欧米だけでなく、韓国や台湾などアジアの国・地域も入っています。
日本の順位を細かく分析すると、外部環境の変化への対応に迅速に対応しきれていない現状が浮かびます。「科学的集積」は24位、「IT総合」は17位と総合順位より上位である一方、「将来の準備」は38位、「ビジネスの俊敏性」は58位にとどまりました。特に「機会と脅威に対する企業の対応」は67位、「柔軟性と適応性」は63位に低迷しています。

国・地域ごとの競争力のランキングは、その国・地域の企業の競争力を色濃く映します。グローバル市場において、日本企業のデジタル競争力は現時点で劣後していると言わざるを得ません。ビジネスアジリティ(ビジネスの俊敏性)を高め、デジタルを効果的に活用してもう一段踏み込んだ変革を推し進めなければ、「コダックモーメント(市場の変化に対応できない状態)」に陥る可能性も現実味を帯びるでしょう。
不確実性の高い時代を拓くビジネスアジリティ
なぜ日本企業のビジネスアジリティはなかなか高まらないのでしょうか。背景にはいくつかの要因が絡み合っていると考えます。1つは組織・文化です。多くの大企業は企業規模を大きくする過程で、組織ごとに専門性を持たせて分業制を敷くことで正確さや標準化を進めてきました。
かつてはこうした形態があるべき姿だったのかもしれません。しかし、非連続で不確実性の高い現代では、専門性や分業制という組織・文化に染まったままでは変化への対応が後手に回りがちです。ビジネスを理解し、開発もわかる。開発が得意かつ、顧客視点で考えられる。こうした複数の専門性を持つ人材や組織が求められていますが、そこまで変革を実践できている企業は限られているのが実態です。
既存のビジネスモデルへの危機感もまだまだ希薄だと言えます。IMDのランキングで「機会と脅威に対する企業の対応」が62位に沈んでいることが危機感の薄さを物語っています。
従来、企業のビジネスモデルは商品・サービスの機能に焦点を当てて発想する「モノ売り」が主流でした。デジタルの発展であらゆるものがネットに繋がる中、商品・サービス自体ではなく、それらを使う顧客の体験や価値に焦点を当てて発想する「コト売り」を起点としたビジネスモデルが世界では広がりつつあります。
コト売りの本質は、顧客との関係性を最初に契約した後からどんどん積み上げていくことです。顧客からのフィードバックをもとに、企業は提供価値を不断に高める。顧客は新たな価値を絶え間なく享受する。そうした関係性を構築することで、非連続で不確実性の高い現代でも顧客層を広げ、ビジネスの成長の好循環を回すことができるのです。
前例踏襲では、外部環境の変化を成長の機会に捉えることは困難です。変化を成長の機会に捉えるには、変化に応じて自らを変革し続けるアジャイルな経営が欠かせません。
アジャイルな経営を実現するには3つの変革がカギになります。1つ目は経営層、事業部門、IT部門の間のサイロを打破する「組織変革」です。2つ目は予め計画を立てる事前計画型だけでなく、仮説を立てて検証を繰り返すことで予見可能性を高める仮説検証型を推進する「ビジネス変革」です。3つ目は組織とビジネスの変革の好循環をつくるエンジンとなる「IT変革」です。
企業の課題に応じて優先順位を付けつつ、これらを三位一体で推進することが、非連続で不確実な時代を拓くビジネスアジリティを生み、アジャイルな経営の土台となり、成長へのステップになるのです。
ビジネスアジリティを不断に高める3つの変革
組織変革、ビジネス変革、IT変革の3つの変革をどのように進めればいいか。それぞれの課題と、課題への打ち手を示します。
サイロを破り、顧客価値を高める組織をつくる(組織変革)
ビジネスに関わるメンバーが、組織のサイロを越えてチームとなることが欠かせません。情報処理推進機構(IPA)が2023年に公表した「DX白書2023」によると、「経営者・IT部門・業務部門が協調できているか」との問いに対し、「十分にできている」との回答は日本が5.9%なのに対し、米国は31.9%でした(図表2)。日本企業の組織変革が不十分であることを示唆しています。

組織のサイロを越えてチームをつくるには、経営や組織のトップの理解や思いが不可欠です。現場主導で組織のサイロを打ち破るのは限界があります。さらに、組織だけでなくデータのサイロも打破しなければなりません。データやAI(人工知能)はツールでしかありません。サイロ化した組織に閉じたデータだけではビジネスは成り立ちません。横串を指し、顧客視点でどんなビジネスが必要なのか。経営や組織のトップが危機感を持ち、変革に自ら乗り出す姿勢も求められるでしょう。
顧客価値を優先し、顧客との関係性を再構築する(ビジネス変革)
従来のビジネスは「売り切り型」、つまり、売れるモノやサービスをどんどん作り、モノやサービスごとにユーザーを増やして売っていくという一過性のものでした。デジタル技術が進展する今、ユーザーの希望を取り込みながらモノやサービスの価値を不断に上げられるようになっています。「顧客と契約することが終わり」ではなく、「契約することがビジネスのスタートである」という発想の転換が求められています。
顧客の価値、市場が求めるニーズは次々と変化します。従来のように事前に計画をきっちり立て、何年もかけてリリースし、どんどん売りましょう、という方法ではもはや持続的なビジネスにはなり得ません。顧客価値を最優先に、新しいビジネスモデルの仮説検証を繰り返すことで顧客との関係を再構築することが、非連続で不確実性の高い時代において持続的な企業価値向上を実現するカギになるのです。
ビジネスの変化に適応できるソフトウェアを開発する(IT変革)
多くの日本企業は社内外向けを問わず、ITベンダーなどの開発企業に要件を提示し、契約の範囲内で完成したものを自ら使う、あるいは顧客に提供する、という受発注の関係が主流でした。契約を守り、コストを意識し、納期を順守する、という前提があるため、「一度きりの完成を目指す」ことを第一の目標に置いてしまう、いわゆるプロジェクト思考に陥ってしまいがちです。
優先すべきは、サービスをリリースした後に顧客からのフィードバックを得て素早く改善を重ねることです。リリース後の保守性や柔軟性の優先度が低いまま開発された場合、ビジネスや顧客要求の変化に対応できない「硬い」ソフトウェアになると考えています。ビジネスや顧客要求の変化に適応するには、動作を変えずにソフトウェアの内部構造を改善するリファクタリングなどの活動を通じ、常にソフトウェアを「柔らかく」しておくことが不可欠です。
ITアーキテクチャの文脈でよく語られるのが「マイクロサービス」と「モノリシック」です。マイクロサービスはそれぞれの機能とデータが独立したサービスとして互いに組み合わさって処理をします。モノリシックは各機能とデータが密接に結びつき、1つのアプリケーションの中で動く仕組みです。
一般的に、変化に柔軟なアーキテクチャはマイクロサービスであると言われています。ただ、小さなプロダクトをリリースし、段階的に規模を大きくする場合、モノリシックなアーキテクチャで素早く構築するケースもあります。初動はモノリシックで開発し、フィードバックを受けて改善を重ねる。徐々にソフトウェアやサービスの規模が大きくなってきたらマイクロサービスのように機能間の結合度を下げる。最初から重厚長大なソフトウェアを目指すよりも、プロダクトのフェーズに合わせたアーキテクチャを選び、変化し続けることが求められます。
ソフトウェアを柔らかく保つには、チーム内で技術や知識の共有を進めることが欠かせません。チームの中で特定のメンバーしかプログラムを修正できない、といったハードルをなるべく排除することで、ソフトウェアの柔らかさを保つだけでなく、チームが「いつでも自分たちのサービスやプロダクトを変えられる」という自信を持てるようになります。そうすることで、チーム自体がプロダクトの一部となり、顧客に価値を提供する存在に昇華するのです。
富士通のコンサルティングアプローチ
3つの変革を最適に一体推進するため、Uvance WayfindersのAgileプラクティスは4つのロール(任務)を定義しています。お客様の課題ごとにコンサルタントが一つのチームを組成して強固な支援体制を整えます。
エンゲージメントリードは全体の責任者として支援を統括するだけでなく、経営層やビジネス部門とのエンゲージメントを通じ、組織の変革やプロダクトデザインを支援します。アジャイルコーチはアジャイルチームへのコーチングや人材育成を担当します。いずれもアジャイルなビジネスや組織運営を実現する土台を整え、発展させる役割を担います。
アジャイルアーキテクトはITアーキテクチャ戦略の立案・検証・定着をけん引します。テクニカルリードはアジャイルチームの開発者に対してトレーニングやコーチングをし、変化に対応できるソフトウェア開発によってビジネスアジリティを継続的に高めます。いずれもアーキテクチャの面からアジャイル開発の環境を整備します。
Agileとは「真の顧客価値を追求すること」
非連続で不確実性の高い時代は当面、続く可能性が高いとみています。今よりさらに先が見通せない未来が私たちを待ち受けているかもしれません。
ビジネスアジリティを高め、今の時代に適用していくためには、自分たちだけでは気づかない様々な課題を客観的に把握する俯瞰力、そして探り当てた課題を解決する「机上の空論」ではない実行力と技術力が要ります。富士通のAgileプラクティスは、富士通での変革の実践知と培ってきた技術力をもとに、お客様の課題に応じてEnd to Endで包括支援します。三位一体の変革によって「真の顧客価値」を不断に追求することこそ成長へのステップとなり、市場での競合優位性を保つことにつながると考えています。
変化への柔軟性を高め、組織やヒト、マインド、ビジネス、ソフトウェアなど、企業にまつわるあらゆるものをアジャイルに進化・高度化することが今こそ、求められているのです。
添田 直之
Naoyuki Soeda
富士通株式会社
Global Customer Success ビジネスグループ Agileプラクティスリーダー
クライアントのビジネスアジリティ獲得に貢献するコンサルティングサービスのデリバリー組織の責任者、並びに、Uvance WayfindersのAgile プラクティスリーダー。システム開発のアジャイルではなく「企業経営変革としてのアジャイル」をテーマに、クライアントとの信頼関係構築やビジネス変革支援、セミナー講演等、多方面で活動中。

森谷 孝志
Takashi Moriya
富士通株式会社
Global Customer Success ビジネスグループ シニアコンサルタント
ビジネスや顧客要求の変化にチームで適応するため、エクストリームプログラミングやDevOpsのプラクティスをトレーニング・コーチングするテクニカルリード。大手電気通信事業、機器・ソフトウェア事業のサービス開発にてテスト駆動開発やペアプログラミングの導入・定着、ソフトウェア開発技術の向上、仮説検証型ビジネスへの変革をサポート。
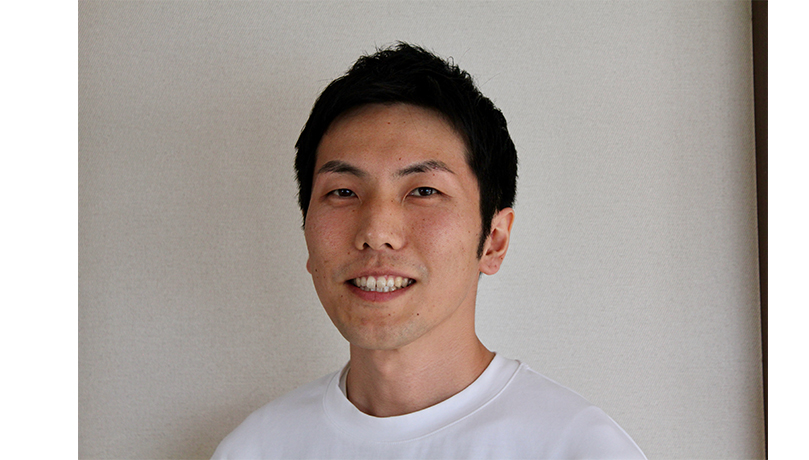
Uvance Wayfinders レポート
富士通のコンサルティング「Uvance Wayfinders」による、アジャイルな経営を構築ためのアプローチを解説。ビジネスアジリティを不断に高める3つの変革、そしてそれを実現する独自の支援体制を紹介します。


